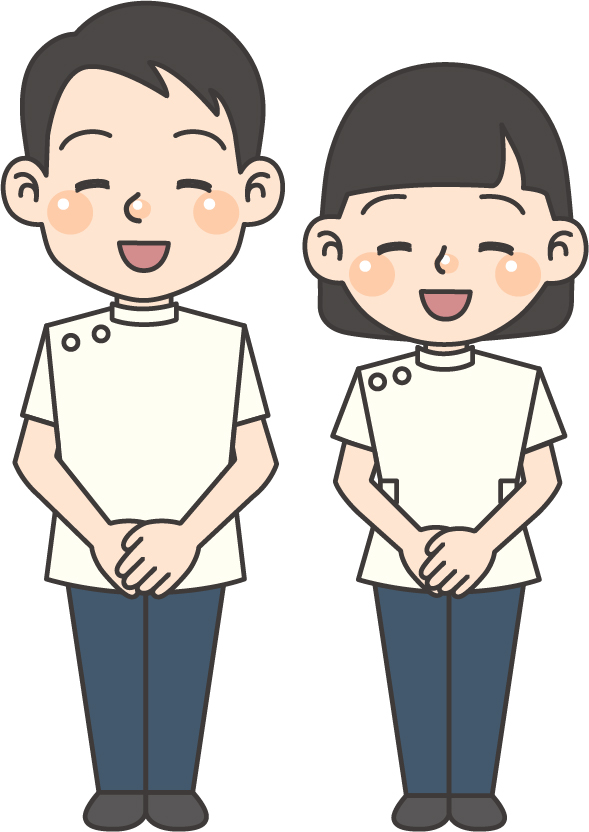
言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist:以下ST)は、医療・福祉・教育といった幅広い領域で活躍する専門職です。「話す・聞く・食べる」といった、人間らしい生活の根幹を支える機能に、アプローチするSTの役割は、身体機能の回復だけでなく、社会参加や自己実現を可能にする支援を行う点にあります。本記事では、失語症と嚥下障害への対応を中心に、STの仕事をより深く理解していただけるよう、臨床での実践例や専門的視点を交えて解説していきます。
言語聴覚士(ST)とは何か
STの役割と専門性

STの主な対象は、言語障害(失語症、構音障害など)、音声障害(声帯ポリープ、喉頭摘出後など)、聴覚障害(感音難聴、補聴器・人工内耳適応など)、嚥下障害(摂食・嚥下機能の低下)です。それぞれの障害に対して、STは詳細な評価を行い、訓練だけでなく、生活場面に即した代償手段の提案、環境調整、家族支援に至るまで介入します。特に、急性期から在宅まで継続的に関わるSTの介入は、機能回復と社会復帰の橋渡し役として重要な役割を担います。
活躍するフィールドと連携職種
STが関わる現場は、急性期病院、回復期リハビリ病棟、療養型病院、訪問リハ、特別支援学校、保育園、介護施設、地域包括支援センターなど非常に多岐にわたります。特に医療現場では、STは患者の機能評価・訓練だけでなく、嚥下造影(VF)や嚥下内視鏡(VE)の実施と解析も担うなど、専門性の高い技術が求められます。また、PT・OT・医師・看護師・栄養士・薬剤師と協働し、統合的なリハビリテーションプログラムを構築する能力も不可欠です。
理学療法士・作業療法士との違い
PTは歩行や移動能力の改善、OTはADLや手作業動作の向上を主眼に置くのに対し、STは「言語」「聴覚」「嚥下」という、より“内的な生活機能”にアプローチします。また、疾患の影響で「自分の思いが伝わらない」「食べられない」状態にある患者は、心理的ストレスも大きく、STはその心理面へのケアも求められます。PT・OTが“動作”を取り戻すのに対し、STは“つながり”や“食の楽しみ”を再構築する存在といえるでしょう。
失語症に対するSTのアプローチ
失語症の種類とその特徴
失語症は、脳の左半球にあるブローカ野やウェルニッケ野など、言語を司る領域の損傷によって引き起こされます。代表的な分類には、発語困難だが理解は比較的保たれるブローカ失語、発語は流暢だが意味が乏しく理解も障害されるウェルニッケ失語、全体的に重度の障害がみられる全失語、読字や書字に特化した障害である純粋失読や失書などがあります。これらはMRIやCT画像所見と合わせて、STが臨床的に評価し、言語の損傷部位と機能の相関を判断していきます。
言語評価の進め方
言語機能の評価では、SLTA(標準失語症検査)やWAB(Western Aphasia Battery)などの標準化検査に加え、日常生活に即した観察評価も重要です。単語理解、文章理解、音読、命名、反復、流暢性などを総合的に評価し、得意・不得意を分析します。また、失語症以外の注意障害、記憶障害、視空間認知の問題が併存していないかを確認し、機能横断的な障害像を把握することが不可欠です。
言語訓練の具体的手法
発語練習と語彙再構築

訓練では、単語レベルから文章構成へと段階的に難易度を調整し、患者の残存機能を最大限活用します。例えば、語想起を促すための意味的ヒントや、音韻的手がかりを段階的に与えるアプローチ(semantic/phonemic cueing)は臨床でも有効です。また、日常生活の中で繰り返し使用する語彙を訓練対象にすることで、実用性を重視した介入が可能となります。
コミュニケーション支援ツールの活用
重度失語症や意思伝達が困難な症例には、AAC(拡大代替コミュニケーション)機器の導入も検討されます。コミュニケーションボード、視線入力装置、タブレット端末などを活用し、「話す」こと以外の手段で意思を伝える方法を確立します。STはその選定・操作訓練・家族指導を通じて、患者のコミュニケーション権を保障する役割を担っています。
嚥下障害に対するSTの対応
嚥下障害の病態と評価方法
嚥下障害は、咽頭・喉頭・食道などの嚥下に関わる器官の運動障害や感覚障害により、食物が気道に誤って入る(誤嚥)リスクが高まる病態です。症状には咳き込み、湿性嗄声、体重減少、脱水、反復性肺炎などが含まれ、放置すれば生命に関わる危険性もあります。STは嚥下障害の有無とその程度を正確に把握するため、嚥下造影(VF)や嚥下内視鏡(VE)を用いた動的評価を実施します。嚥下の各ステージ(先行期、準備期、口腔期、咽頭期、食道期)ごとに障害部位を特定し、訓練内容を明確化します。
嚥下訓練の種類と目的
間接訓練と直接訓練の違い
間接訓練では、アイスマッサージや嚥下反射誘発、呼吸訓練、咽頭周囲筋の筋力強化(Shaker法、頭部挙上訓練など)を通じて基礎機能の向上を図ります。直接訓練では、実際に食物を摂取しながら、安全な嚥下動作を再獲得することを目指します。誤嚥リスクを避けるため、食形態・一口量・姿勢の調整を行いながら段階的に訓練を進めます。
食事形態の調整と工夫
嚥下障害のある患者に対しては、ユニバーサルデザインフード(UDF)やとろみ剤を活用し、誤嚥のリスクを抑えながら必要な栄養を確保することが重要です。また、姿勢調整(頸部屈曲位、側方傾斜位など)や食具の工夫、食事時間・雰囲気への配慮も、嚥下を助ける重要な要素です。STは患者の生活環境を把握し、家族・介護職とも連携しながら個別対応を行います。
多職種連携による嚥下支援
嚥下支援はST単独では完結せず、多職種との連携が成功の鍵を握ります。医師の診断と治療方針、管理栄養士の栄養設計、看護師・介護職の食事介助方法、歯科衛生士の口腔ケアなど、各職種の専門性が嚥下機能の維持・改善に寄与します。STは、これらの中心となり、「誰が、いつ、どのように関わるか」をマネジメントするコーディネーターとしての役割も担っています。
STが担う今後の課題と可能性
高齢化社会とSTのニーズ
2025年以降、日本は「超・高齢化社会」に突入し、失語症や嚥下障害を有する高齢者の数は飛躍的に増加すると予測されています。それに伴い、急性期・回復期病院におけるSTのニーズはもちろん、在宅や地域包括ケア領域においても、STによる介入の重要性が高まります。施設に通えない高齢者にもリハビリを届ける「訪問ST」や、地域での予防啓発活動も今後拡大が期待される分野です。
テクノロジーとリハビリ支援の融合
近年ではAIによる音声分析、VRを活用した訓練プログラム、失語症用アプリやWEBベースの自己訓練プラットフォームなど、テクノロジーの活用が急速に進んでいます。これにより、病院外でもSTの訓練が可能となり、訓練の継続性やモチベーションの向上にもつながります。STにはこれらのツールを評価し、適切に導入・指導するスキルも求められる時代になってきました。
地域でのSTの役割拡大
STは今後、医療・福祉の枠を超え、教育・行政・地域活動などへと活動の幅を広げていくことが期待されています。例えば、地域包括支援センターでのスクリーニング業務や、小中学校における発達障害児の支援、高齢者施設での予防教室の運営などが挙げられます。多様化する社会ニーズに応えるため、STには臨床力だけでなく、教育・啓発・企画運営といったマネジメント能力も求められるようになっています。
まとめ
STは、病院という枠にとどまらず、地域社会のさまざまな場面で「ことば」と「食」を支える重要な役割を担っています。今後はより柔軟で創造的な働き方が求められると同時に、専門性を活かしたリーダーシップが社会全体から期待されています。
整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎
https://8e0f6.hp.peraichi.com
無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy
施術案内ページはこちら⬇︎
https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/
訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎
https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/


