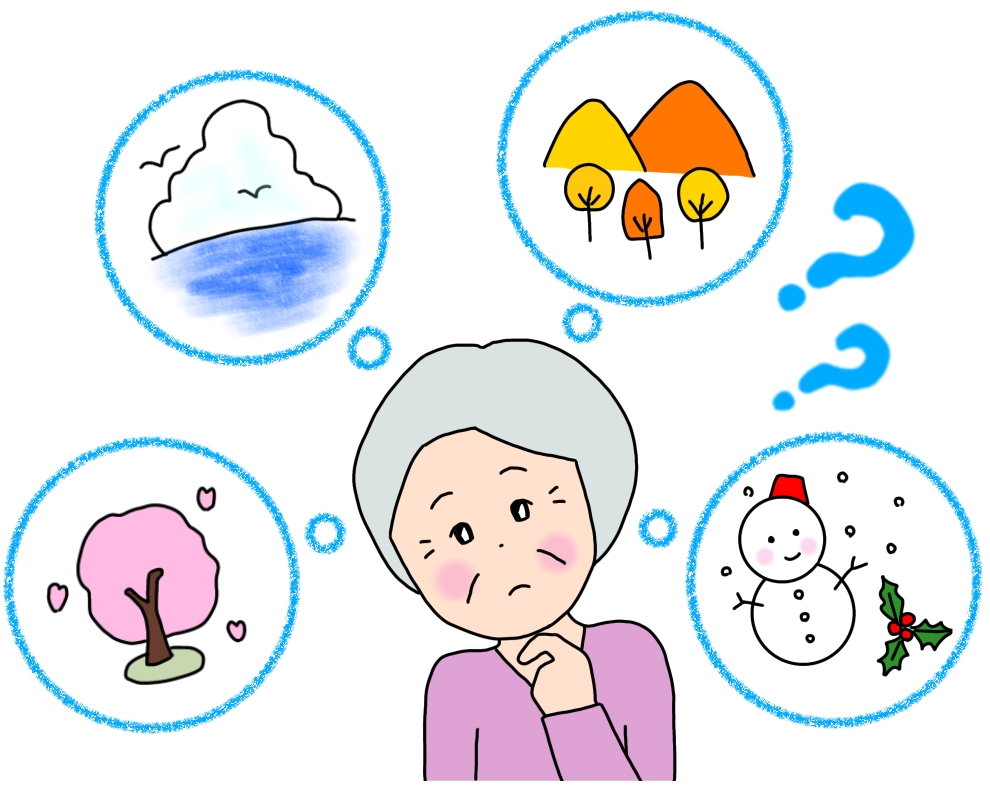
高齢化が進む現代社会において、認知症は身近な疾患となりつつあります。しかし、「認知症=アルツハイマー病」という誤解がいまだに根強く存在しています。認知症はあくまで症候群(症状の集合体)であり、その原因となる疾患は複数存在します。その中でもパーキンソン病は、運動障害の印象が強い一方で、実は認知機能障害も引き起こし得る疾患であることは、あまり知られていません。結果として、アルツハイマー病と混同されることも少なくありません。
本記事では、パーキンソン病とアルツハイマー病の明確な違いを深掘りし、両者の診断・治療・ケアにおけるポイントを明確にします。混同されやすい背景を踏まえた上で、臨床現場での鑑別の実際や多職種連携の在り方についても掘り下げていきます。
パーキンソン病とは何か?その定義と特徴
パーキンソン病(Parkinson’s disease)は、進行性の神経変性疾患であり、特にドパミンを産生する神経細胞の変性・脱落が中心病変です。運動症状が注目されがちですが、実際には精神症状や自律神経症状、認知機能障害など多彩な症状を呈します。中枢神経系全体に波及する複雑な病態を有していることが特徴です。
中脳黒質の変性とドパミンの関与
パーキンソン病では、脳幹の一部である中脳の黒質緻密部において、ドパミン作動性神経細胞が著しく減少します。これにより、大脳基底核との情報伝達が遮断され、運動の開始や制御が困難になります。さらに、レビー小体と呼ばれる異常タンパク質(α-シヌクレイン)の蓄積が認められ、これが神経細胞死の誘因となることもわかってきました。近年では、腸管神経系から中枢神経系へ病理変化が波及する「ブラク仮説」も注目され、パーキンソン病は全身性の神経疾患として再定義されつつあります。
運動症状:振戦・固縮・無動・姿勢反射障害
パーキンソン病の診断的な指標ともいえる運動症状には、①安静時振戦、②筋固縮、③無動(寡動)、④姿勢反射障害があります。これらは「運動の質」だけでなく「運動の数」も減少させ、生活機能を著しく制限します。例えば、歩行ではすり足・小刻み歩行・突進現象が見られ、転倒や骨折のリスクが高まります。早期には一側性に出現することが多く、徐々に両側性へと進行します。
非運動症状:認知機能の変化や自律神経症状
非運動症状は、患者のQOL(生活の質)を大きく左右する要因です。認知機能の低下は進行期に多く見られますが、早期から注意障害や遂行機能障害が潜在的に存在することもあります。また、幻視や妄想、睡眠行動異常(REM睡眠行動障害)、うつ状態などの精神症状も一般的で、アルツハイマー病との鑑別をさらに困難にします。さらに、便秘・排尿障害・起立性低血圧などの自律神経障害も含め、多面的な症状マネジメントが必要となります。
認知症との違い:混同されやすい理由
認知症は「原因にかかわらず、獲得された認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす状態」を指します。したがって、パーキンソン病であっても、認知機能の障害が一定以上に達すれば「認知症」と診断され得ます。そのため、症状の重なりが多く、臨床上の見極めが求められます。
認知症に見られる記憶障害の特徴

アルツハイマー病における記憶障害は、特に「新しい情報の記銘障害」が中心です。海馬を中心とした側頭葉内側の萎縮により、エピソード記憶が障害されます。特徴的なのは、ヒントを与えても思い出せない「真の記憶障害」です。また、時間・場所・人物の順に見当識障害が出現し、日常生活全体に支障をきたすようになります。
パーキンソン病における認知障害の特徴

パーキンソン病では、記憶障害よりも「注意・遂行機能の障害」や「視空間認知の障害」が先行することが多いです。計画立案の困難、柔軟な思考の低下、環境適応の難しさといった症状が目立ちます。これらは前頭葉-大脳基底核回路の機能障害と密接に関係しています。また、パーキンソン病認知症(PDD)やレビー小体型認知症(DLB)では幻視や日内変動、睡眠障害の合併も多く、アルツハイマー病との鑑別に役立ちます。
なぜ両者が混同されやすいのか?
混同の最大の原因は、「認知症」という言葉が疾患名として独立して扱われやすいことにあります。さらに、高齢者では複数の神経疾患を併発していることも多く、パーキンソン病とアルツハイマー病を同時に持つ例も珍しくありません。加えて、初期段階では症状が非特異的であり、正確な鑑別には専門的知見と検査が必要です。
アルツハイマー病との比較:症状と進行の違い
両者の違いを明確にするためには、疾患の「発症様式」「進行速度」「脳画像上の変化」「症状のパターン」などを総合的に把握する必要があります。
発症年齢と進行速度の違い
アルツハイマー病の発症は65歳以上の高齢者に多く、緩やかに記憶障害から始まるのが一般的です。一方、パーキンソン病は50~60歳代に発症しやすく、運動症状が先行するため、初期段階での認知機能低下は目立ちません。ただし、発症から10年以上経過すると認知症が出現することも多く、「時間軸」も鑑別のヒントになります。
MRI・PET検査による脳の画像所見
アルツハイマー病ではMRIにて内側側頭葉の萎縮、特に海馬の容積減少が顕著です。FDG-PETでは後部帯状回および頭頂葉の代謝低下が認められます。一方、パーキンソン病では黒質の変性が主体であり、DaTスキャンにより線条体のドパミントランスポーター減少が観察されます。これらの画像検査は、鑑別診断において不可欠な手段です。
記憶障害 vs 運動障害:初期症状の対比
アルツハイマー病では「物忘れ」を主訴に医療機関を受診することが多く、家族が異変に気づくケースも少なくありません。対して、パーキンソン病では、手の震え、動作の遅さ、姿勢の不安定さといった身体的な異常を訴えることが多く、認知症の存在が見過ごされやすい傾向にあります。問診時に初期症状を丁寧に拾い上げることが、正確な鑑別につながります。
鑑別診断と治療方針の違い
鑑別診断の正確性は、今後の治療計画・予後予測・介護支援方針を左右します。特に、進行性の疾患に対しては、初期段階での判断がその後のQOLに直結します。
鑑別診断に用いられる検査方法
神経心理学的検査(ADAS-cog、FAB、TMTなど)をはじめ、MRI・CT・PET・SPECT・DaTスキャンといった画像検査を組み合わせることで、鑑別精度を高めます。また、脳脊髄液検査によるアミロイドβやタウ蛋白の測定はアルツハイマー病の病態把握に有用です。さらに、夜間の睡眠ポリグラフ検査や自律神経機能検査も、パーキンソン病の診断補助となります。
治療薬の違いとその効果
アルツハイマー病では、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジル、ガランタミン)やNMDA受容体拮抗薬(メマンチン)が用いられます。これらは症状の進行抑制を目的としたもので、根治には至りません。パーキンソン病では、レボドパ製剤やドパミンアゴニストが第一選択となり、運動症状の軽減に高い効果を示します。認知障害が出現した際の薬剤選択は、過鎮静や幻視誘発を防ぐため、非常に慎重を要します。
多職種連携による対応の重要性
どちらの疾患も、単一の医療職種では対応しきれない複雑性を有しています。医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤師、ケアマネジャーなどの多職種による情報共有と協働が、患者の生活機能維持に不可欠です。特に在宅移行や施設介入を視野に入れる場合、福祉制度や地域資源の活用も重要な要素となります。
まとめ
パーキンソン病とアルツハイマー病は、いずれも高齢者に多く見られる進行性の神経疾患ですが、その病態、初期症状、進行様式、治療法には明確な違いがあります。にもかかわらず、非運動症状や認知機能の低下といった共通項により、しばしば混同されがちです。誤診は、適切な治療や支援体制の構築を妨げるため、正確な鑑別が非常に重要です。
専門的な知識に基づいた評価と、多職種連携による包括的な対応が求められる今こそ、疾患ごとの違いを深く理解することが医療者にとって不可欠です。疾患に対する正しい知識と適切な支援が、患者と家族の生活の質を守る鍵となります。
整形外科疾患に対する勉強会案内はこちら⬇︎
https://8e0f6.hp.peraichi.com
無料勉強会やオンラインコースについては代表高柳の公式ラインから⬇︎
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=397vgsxy
施術案内ページはこちら⬇︎
https://neuroplasty-tokyo.com/shop-rehab/
訪問リハビリ案内ページはこちら⬇︎
https://neuroplasty-tokyo.com/home-rehabilitation/


